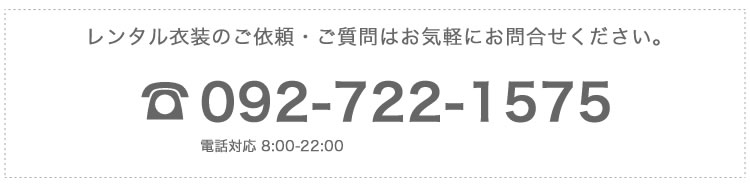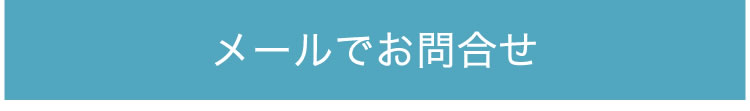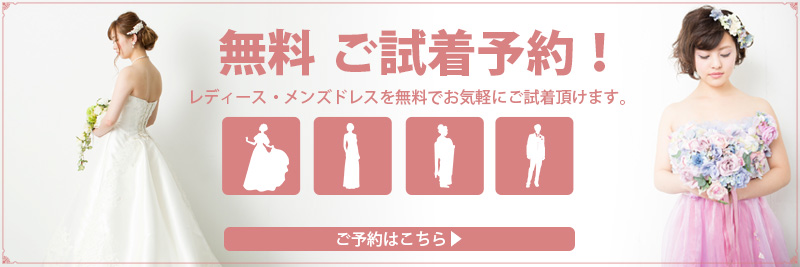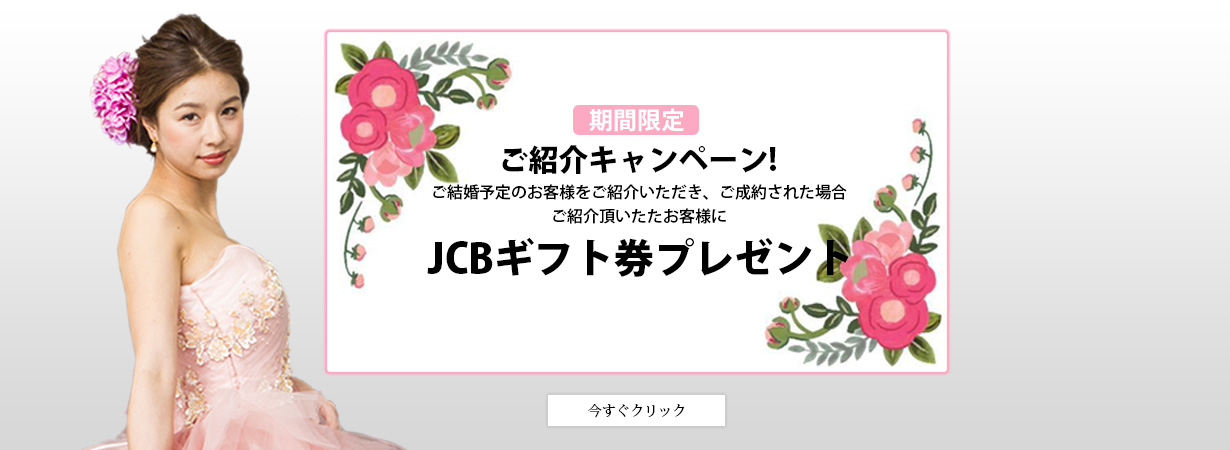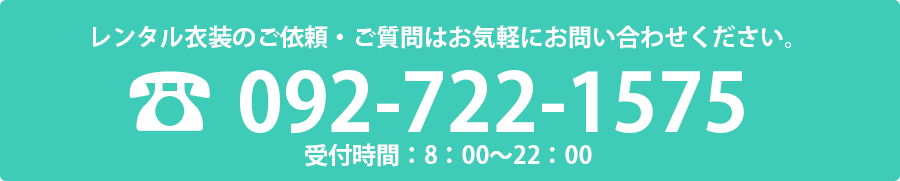和装レンタル福岡(白無垢・色打掛)神社婚の流れ
日本ならではの神社婚。
家族や友人と共に、人生の節目としてけじめがつけられる神前式の流れをご紹介
1●参進(さんしん)

厳かな空気に包まれて一歩一歩、本殿に向かう
挙式に参列する人が神殿に入っていく最初の儀式。
鳥居をくぐることで神域に入るという意味を持つ。神職、巫女に先導され参列者全員が神殿まで歩いていくこともある。
2●入場・着席
新郎新婦は真ん中に、ゲストは親から前に座る
神前に向かって右側には新郎、左側には新婦が着席する。
ゲストはご神体に近い方から親、兄弟、親族の順に座っていく。友人や知人が参列可能な場合は後ろに座ることが多い。
3●修祓(しゅうばつ)

すべてのものを清め神様をお迎えする
神前式に先立ち、神様をお招きする前に供物をはじめ、新郎新婦、参列者などを祓い清めるための儀式。
全員が起立し、頭を下げて斎主から大麻(おおぬさ)でお祓いを受ける。
4●斎主一拝(さいしゅいっぱい)
神様に対して挙式の始まりの挨拶をする
参列者全員で、これから祭儀を開始しますと、神様に対して挨拶のために一礼をする儀式。
参列者は神前に向きを変えて、斎主に合わせて、深くゆっくりと一礼する。
5●祝詞奏上(のりとそうじょう)
ふたりの結婚報告を行い感謝と崇敬の意を伝える
神様と人との「仲執り持ち(なかとりもち)」である斎主が、新郎・新婦に代わって神様に結婚の報告を行う。
また、ご加護やご利益を願う言葉を神様に向け奏上する。
★祝詞にはこんな意味がある
結婚の報告と同時に、今後ふたりがいつまでも仲良く、助け合い、子孫の代まで繁栄し、幸せに人生を歩んでいけるように神様にお願いをしている。
6●三献の儀(さんこんのぎ)

夫婦が永遠の契りを交わす。酌み交わすたびに縁が深まる
大中小の3つの盃を新郎と新婦が交互に三口で酌み交わす。
結婚を祝福して、神様からお神酒をいただき、それを飲むことで神様の気を体の中に入れる意味がある。
★3つの盃にはこんな意味がある
小が先祖への感謝、中が新郎新婦の誓い、大が家族の安泰や子孫繁栄の願いを表し、重ねて杯を酌み交わすことで縁を結ぶという意味合いもある。
7●指輪交換

お互いに指輪を交換する。現代では一般的な儀式
巫女が指輪を運び、新郎から新婦へ、新婦から新郎へと、それぞれ相手の左手の薬指にはめる。
結婚を成立させる儀式ではないため、行わなければならないものではないが今では一般的。
8●誓詞奏上(せいしそうじょう)

ふたりで神前に進み、神様の前で誓いを立てる
神社によって綴られている言葉は異なるが、新郎が夫婦の歩みたい道が書かれたものと自分の名前を読み上げた後、新婦が名前を述べる。
誓詞は、ひな型が用意されている。
9●玉串拝礼(たまぐしはいれい)

玉串を通して神様に願いを届ける
榊の枝に紙垂(しで)を付けた玉串を新郎新婦が受け取り、ふたりで揃って玉串を置く案(机)まで進み、願いを込めて奉奠(ほうてん)。二拝二拍手一拝をし、席に戻る。
10●親族盃の儀

両家が親族となった誓いの杯を交わす儀式
巫女が両家の上座から順にお神酒を注いで回り、両家列席者全員の杯にお神酒が注がれたところで一同起立し、一斉に三口で飲み干す。両家が親族となったことを意味する。
神社での神前式のギモンQ&A
神社での挙式は列席経験が少ないこともあって、しきたりなどがわからないことが多いもの。
不安を解消して当日を迎えて。
Q.友人も列席できるの?
A.

親族のみしか列席できない神社もあるが、最近では友人や知人の列席を認める神社も増えている。
また、収容人数によって異なるので問い合わせてみて。
Q.お金を支払うタイミングはいつ?
A.
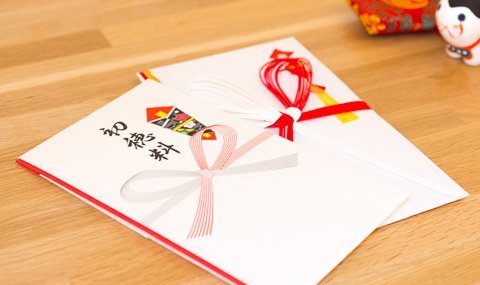
挙式料は神様にお供えをする「初穂料(はつほりょう)」。
神社によって納め方が異なるが、原則当日までに現金で納める。
その際、熨斗(のし)袋の準備を忘れずに。
Q.バリアフリーなど設備面は大丈夫?
A.

段差がある場所が多いのが現状だが、最近はスロープもあり車椅子の対応などバリアフリーの神社も増えている。
事前に動線などを含めて相談しておくと安心。